
あらすじ
「魔女が倒れた。もうダメみたい」中学3年になった少女まいに、突然の知らせが届く。
おばあちゃんの家へ向かう車の中でママから聞かされたおばあちゃんの訃報。
"魔女"とはママのママ、英国人の祖母のことだった。まいは2年前のおばあちゃんと一緒に暮らした日々へ
想いを馳せる・・・
制作国 :日本
公開日 : 2008年6月21日
上映時間 :115分
配給 :アスミック・エース
監督: 長崎俊一
脚本: 矢沢由美 長崎俊一
出演者
サチ・パーカー 高橋真悠 りょう
西の魔女が死んだ
2009年8月17日 更新

あらすじ
「魔女が倒れた。もうダメみたい」中学3年になった少女まいに、突然の知らせが届く。
おばあちゃんの家へ向かう車の中でママから聞かされたおばあちゃんの訃報。
"魔女"とはママのママ、英国人の祖母のことだった。まいは2年前のおばあちゃんと一緒に暮らした日々へ
想いを馳せる・・・
制作国 :日本
公開日 : 2008年6月21日
上映時間 :115分
配給 :アスミック・エース
監督: 長崎俊一
脚本: 矢沢由美 長崎俊一
出演者
サチ・パーカー 高橋真悠 りょう
おれは上野が嫌いだ。渋谷はもっと嫌いで、つまり人ごみが好きじゃない。
浅草のように街自体が文化的な匂いを持っている場所ならまだ許せる。
だが、どこを見ても平面で、たえずBGMがわりに音楽が流れていて、同じような格好をした若者が我が物顔で闊歩する。
自分の感覚がその他大勢の中に埋もれていくあの感じが嫌だ。
おまけにそういうところに限って道が分かりにくくなっていて、携帯の地図を見、駅前の地図看板を見、実際に景色を見ると一致しないことが多い。
ああ、おれは映画が観たいだけなのに。何度も往復して、曲がり角を一本飛ばしていたことに気付く。
注意していないと通り過ぎてしまうひっそりとした小道。ビール瓶が道の脇にあり、手書きの看板が目立つ。
喧騒から、その他大勢から遠ざかっていくのが分かる。おれの勘が言う。「この先だ」と。
案の定、その映画館は、あった。時代に取り残されたような白い建物、上野スタームービー。
中に入るとウチのオカン位のおばちゃんが「券売機で買ってね」と言う。今日は一日だから1000円のはずだ。
「一般」のボタンを押そうとすると、「ごめんね。今日はシニアの方押してくれる?ごめんねえ」割引き用のボタンがないから、常に1000円の「シニア」ボタンで代用してるらしい。
申し訳なさそうに笑うおばちゃんの顔を見て、ああ、おれは元旦のあわただしさから抜け出し、一人映画を観にきたのだなあ、と実感するのだった。
「魔女が倒れた。もう駄目みたい」
そんなナレーションから始まるこの映画は、中学一年生のマイと山に住む優しいおばあちゃんとの心の交流を描く物語。
タイトルの「魔女」とはこのおばあちゃんのことで、感受性が強く人となじめない女の子のマイはおばあちゃんのもとで魔女修行をする。
というと一見ファンタジーのようだが、魔法も出てこないし、箒で空を飛ぶこともない。
規則正しい生活と、真っ直ぐな精神を持つことが魔女の条件という詭弁にも聞こえるおばあちゃんの言葉のもと、二人の共同生活が特に大きなドラマもなく淡々と描かれる。おれが最初に感じたのは、「あ、これは宮崎アニメだな」ということ。
といっても「魔女の宅急便」ではなく、全体の描かれ方がジブリ的なのだ。
もっと具体的に言ってしまうとピュア過ぎる語り方をしている。おばあちゃんのロハスな生活はどこからお金が出ているのか、なぜ広大な山の土地を所有しているのかなどは作中で語られず、毎日ハーブティなんかをいれて、気が向いたら畑の野菜や苺をとってジャムにしたりする。
何不自由なくオシャレな生活(この辺りは女性のほうが受け入れ易いかも)がディティール(細部)にこだわりながら丁寧に描かれる。
マイがレタスについた虫を見つけてビックリするのは「千と千尋」っぽいし、ジャムを塗ったサクサクのパンや取れたて野菜を挟んだサンドイッチはよだれが出るほど美味しそうで、「ラピュタ」の目玉焼きパンを想起させる。
食べ物に対する感覚に監督の並々ならぬ情熱を感じた。そういう日常を描いておいて、ラストはタイトルがすでに示している。
すなわち「魔女」の死。OPのナレーションが終わると学校の制服を着たマイがおばあちゃんの最後を看取りにおかあさんと「魔女」のもとに向っている。
ファーストシーンがラストシーン(のちょっと前)になっていて、この「死」が前提となる構成は黒澤の「生きる」もっと遡ればワイルダーの「サンセット大通り」のような古典がある。
しかし両者はそれがさりげなく上手いのに対し、今作はタイトルとナレーションとファーストシーンで「魔女」の死を強調しているのはくどい。
そこまで思わせぶりにする必要はなかったように思う。構成も残念。
まるでCMのように一つ一つの見せ場を丁寧に作っているのだが、一つが終わると、また山の生活の新しい発見があって、その繰り返しになってしまっている。
映画といってもドラマなのだから、最低限のリズムがあり、一つの見せ場が二つ、三つと新たなステージに誘導するように見せなければならない。
ありていな言い方だと「伏線」もその一つ。
映画はドキュメントではなく、ストーリーのドミノ倒しなのだから。ジャムを作る→ハーブティーを入れる→良く眠れるようにおまじないをする→おばあちゃんとおしゃべり→野菜をとってくる、では環境ビデオを見せられている気分になる。
オーラスでは観客がみんな泣いていた。いや、正確には女性客が泣いていて、男性客はう〜んという顔をしていた。
たしかにラストシーンだけ見てもウルッとくるところはある。
だがもう少し結びつく何かがないと(いや確かにマグカップという伏線はあるのだが)それまでの生活が生きてこない。
泣いている人は、おばあちゃん、素直な孫、自然、ロハスな生活、憧れ、別れ、そしてラストの・・・。
という綺麗な綺麗な精神が高尚だったから泣いたのではないか。
この映画で泣ける自分を人に言いふらしたくなるようなそんな自分にも酔えるのが女性で、男性より圧倒的に思い込みの強い人種であると改めて思い知らされた。
もしかしたら劇中の二人の関係にもそんな一面があったのかもしれない。
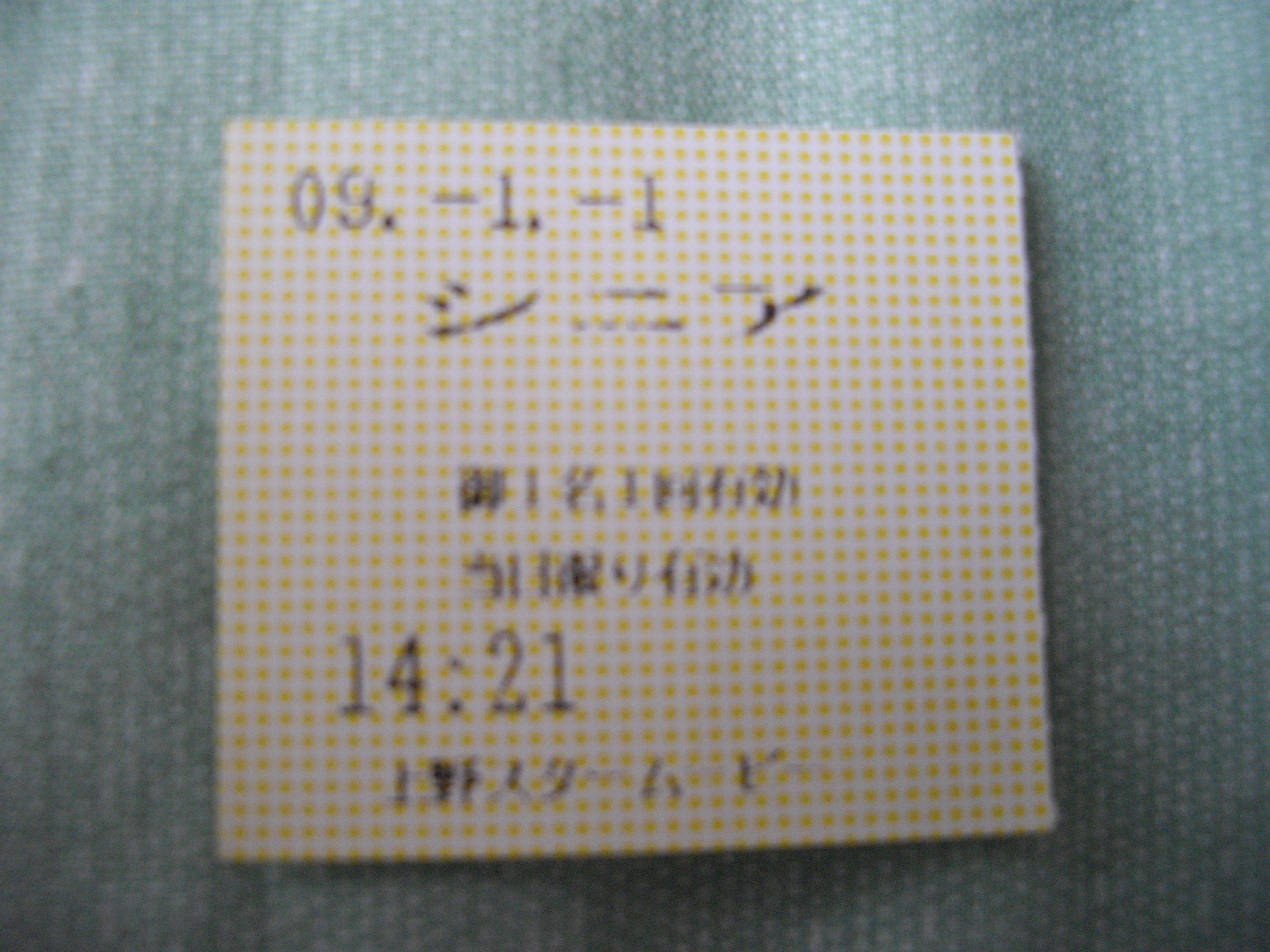
2009年1月1日 上野スタームービーにて鑑賞